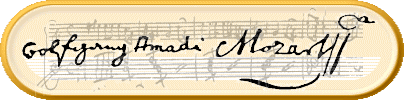
| (ここは)どう表現されているか、ご存じですね。愛に溢れてどきどきする胸も、すでにオクターブ並行の二つのヴァイオリンで示されています。…おののきも、よろめくさまもみられますし、ふくらむ胸が高まる有様もみられますが、これはクレッシェンドで表現されます。…ささやきも溜息も聴こえます…これは弱音器つきの第一ヴァイオリンとフルート一本のユニゾンで表現されます。 (1781年9月26日、モーツァルトの父宛の書簡 ―『後宮からの逃走』のベルモンテのアリア「ああ、なんと不安な、ああなんと燃えるように」について) |
| (ド・シャボ公爵夫人の邸に)行ってみると、全然暖めてない、氷のように冷たい、暖炉もない大きな部屋で半時間も待たされました。やっとド・シャボ公爵夫人が大変なお世辞をふりまいて現れました。そして、彼女自身のピアノは調律してないので、そこにあるピアノで弾いてくれないか、とぼくに頼みました。で、ぼくは言いました。「喜こんでなにか弾きたいのですが、いまは弾けません。指が冷えきって感覚が麻痺していますから…。」ぼくは、少なくとも火の入っている暖炉のある部屋に通してくれるように夫人に頼みました。「ほんと、あなたのおっしゃる通りですわね。」と返事があっただけです。…そこでぼくは、たっぷり一時間待たされました。窓も扉も開け放しで、ぼくは手ばかりでなく、身体も足もすっかり冷たくなってきました。早く切りあげようと、ぼくはついにそのおんぼろピアノを弾き始めました。ところがいちばんしゃくにさわったのは、夫人や紳士たちがみんなデッサンに夢中で、いわば椅子やテーブルや壁を相手に弾かなければならなかったことです。こんなひどい状態に、我慢しきれなくなって、ぼくは『フィッシャーの変奏曲』(*)を弾き始めていましたが、半分弾いて、立ち上がりました。…公爵夫人はぼくを行かせてくれようとせず、、また半時間も、ご主人が来るまで待たされました。ところがご主人はぼくのそばに坐り、細心の注意を払って聴いてくれるのです。それでぼくは寒さも頭痛もすっかり忘れ、おんぼろピアノのことさえ気にしないで─上機嫌のときと同じように弾きました。たとえヨーロッパの最上のピアノを与えられても、聴き手がなにもわからないか、わかろうとしないか、ぼくの弾くものに共感できなければ、ぼくはまったく喜びをなくしてしまうでしょう。[*=K.179] (1778年5月1日、モーツァルトの父宛の書簡 ) |
| 死は(厳密に言えば)ぼくらの人生の真の最終目標ですから、数年来ぼくは、人間のこの真実の最上の友と非常に親しくなっています。その結果、死の姿はぼくにとって、もはや怖ろしくないばかりか、大いに心を静め慰めてもくれます! そしてぼくは、死こそぼくらの真の至福への鍵であることを知る機会(ぼくの言う意味がおわかりですね)を与えてくれたことを神に感謝しています。─ぼくはいつも床につくとき、(まだこんなにも若いのに)ことによると明日は、もう生きていないかもしれないと思わないことはありません。けれどもぼくを知っている者で、ぼくが人とのつき合いで不機嫌だとか悲しげだとか言える者はいないでしょう。そして、ぼくはこの幸福を、毎日創造主に感謝しています。 (1787年4月4日、父の重体の知らせに対する父宛の書簡) |
| 私はあのモーツァルトの小柄で、燃える才気の炎に照らされた輝いた顔を、今でも忘れることは出来ない。それを形容することは、太陽の光を正しく描写するほどむつかしいことである。彼はモールの付いた赤い毛皮の帽子を被って舞台に立ってゲネプロを指揮したが、ベヌッチが「もう飛ぶまいぞ」と声の限りに生き生きと歌った時、私はモーツァルトのすぐ傍に立っていたのであるが、彼は小さい声で「ブラヴォ、ブラヴォ、ベヌッチ」と叫んだ。そして彼が最後の「ケルビーノに勝利あれ、偉大な武勲に栄光あれ」を見事な大きな声量で歌い終ったときは、みんなが感動して舞台の上の歌手たちも、オーケストラの音楽家たちも、まるで電気でもかけられたように夢中になって、ブラヴォ!、ブラヴォ!、大モーツァルト万歳と叫んだ。オーケストラはいつまでも拍手と弓で譜面台を叩きつづけていた。 (マイケル・ケリー「回想録」/ロンドン、1826年刊より) |
| あなたへの感謝の心は、ありのままにいって次の一事につきます。すなわち、あなたを聴くとき私はいつも、陽光と嵐、昼と夜、その両面をともに具えつつ、しかも善にして調和ある創造の世界の入り口に立たしめられる、同時に私は、二十世紀に生きる人間として、聴く度毎に高慢ならざる勇気を与えられ、過度ならざる速度(テンポ)を持たしめられ、退屈ならざる純粋さを贈られ、不正ならざる平和を与えられるのを実感する、このことなのです。 あなたの音楽的弁証法を耳にしていれば、若くもなり年老いることも出来る。勤労にいそしむことも、憩うことも出来る。歓び楽しむことも哀しむことも出来る。一言で言えば、生きることが出来るのです。 (カール・バルト「モーツァルトへの感謝の手紙」/1955年12月23日バーゼルにて) |
| 今日はよい日だ。ふたたび生の味わいが感じられそうな気がする。生はふたたび可能になるばかりか、ふたたび親しげになるようにさえ思われる。 この日の上に、私の色とりどりの生の手帳のこの一ページの上に、私はひとつの言葉を書きつけたい。《世界》とか《太陽》とか、魔力と輝きに満ちた言葉、響きに満ち、豊かさに満ち、充溢を超えて充ちあふれ、豊饒を超えて豊かな言葉、完璧な成就、完全な知識を意味する言葉を。 するとその言葉が私の心に思い浮かぶ。この日のための魔術的なしるしが。それを私は大文字でこのページに書きつける─モーツァルトと。つまり、世界にはひとつの意味がある。それは音楽という比喩の形でわれわれに示されるのだ。 (ヘルマン・ヘッセ/1920年の日記より) |
| モーツァルトのピアノ・ソナタは、ピアノ音楽全ての可能性を表現しきっているように聴こえてくる。つまりひとつのテーマや表現イメージを音楽的に構築して、その音楽を呈示するというのではなく、音はあくまで自由に、ある瞬間は悲しく、ある瞬間は遊び、ある瞬間は天使の如くやさしく、それら全ての要素が奇跡の如くピアノ音楽の美に向かっている。 (赤塚不二夫「続私のモーツァルト」帰徳書房1977年刊より) |
| モーツァルトの場合は、世にも素純な魂が、デーモンの導きを、情熱を内に包んで静かな光とした類まれな美しい音楽を人類に与えた。このような働きを成し遂げた人間は、いずれ地上での、現実の生活者としては、必然的に不幸であった。 (東山魁夷「続私のモーツァルト」帰徳書房1977年刊より) |
| 「軽さが沈み、重さが浮かぶ」あの変転きわまりない旋律は、またなんと愛らしく、なんと明るく澄みわたっていることか。それは、みやびとか甘美などという、なまやさしいものではない。死の影が、ときおり、ふと、秋風のようによぎってゆく。だが、それはほんの一瞬であり、たちまち、天性の陽気さや優しさに打ち消されてしまう。どことして退屈な重さやめめしい涙はなく、生き生きとした生命力がほとばしり出ている。それは、子供の遊びのように、同じテーマであっても、少しずつ違って、新鮮である。どの音符ひとつをとっても、つねに作曲者の愛の響きを感じないものはない。まさに人間の歌そのものだった。 (高橋英郎「人間の歌モーツァルト」白水社1977年刊より) |
| わたしがモーツァルトの音楽に驚き、感じたものは、その超人的な愛情でした。それは人間の知恵や理屈を超えている。ただ魂で感じられる実在の大きな愛情です。この愛情にひそむものは、人間の深い悲哀でした。この世に生まれて、やがて死んでいく、この人生のはかなさ、さびしさ、そこはかとない、しみ入るような哀愁です。この哀愁を短音階のみならず、モーツァルトは、実に長音階において、深い愛情のなかに表現したのです。生も死も、人間がどうしようもない大自然の営みでした。その必然としてモーツァルトの哀愁とともにあるものは、しみじみとした諦観です。 (鈴木鎮一「愛に生きる」講談社現代新書1966年刊より) |
| モーツァルトの場合、その音楽の背後にある哀しみはもっと果てしなく遠いものである。それは、もはや「存在すること」の哀しみではなかろうか。太陽や惑星や月がそこに「在る」ことの哀しみであり、人や動植物がそこに「生きている」こと自体の哀しみとでも言えようか。すべては、やがて衰退し、消滅していく存在であり、その天の掟に逆らえるものは何ひとつないからである。そして、生命には有限なるがゆえの一瞬の輝きがあり、その煌きは有限なるがゆえに尊く、いとおしい。 (福島章恭「モーツァルトをCDで究める」毎日新聞社2002年刊より) |
| モーツァルトAnthology(選曲集)はこちら |
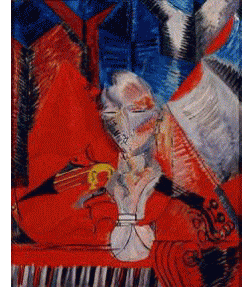 |
Raoul Dufy(1877~1953) 生涯モーツァルトを愛したフランス近代画家の巨匠ラウル・デュフィは、音楽とモーツァルトへのオマージュを何点か残している。 『モーツァルトに捧ぐ』1915年 『赤いヴァイオリン』1948年 『黄色いコンソール』1949年 『ヴァイオリンのある静物』1952年 『赤いヴァイオリン』1946年 『モーツァルト頌』1952年 『コンサート』1948年 |
| 私のモーツァルト30選 |
| (K番号または曲名をクリックするとコメントが出ます。) ケッヘル番号についてはこちらをクリック。 |
(その1) (その2) 「日々雑感」に掲載した曲をこちらに纏めました。 |
 |
| モーツァルトの墓標(ウィーン聖マルクス墓地) |
 |
 |